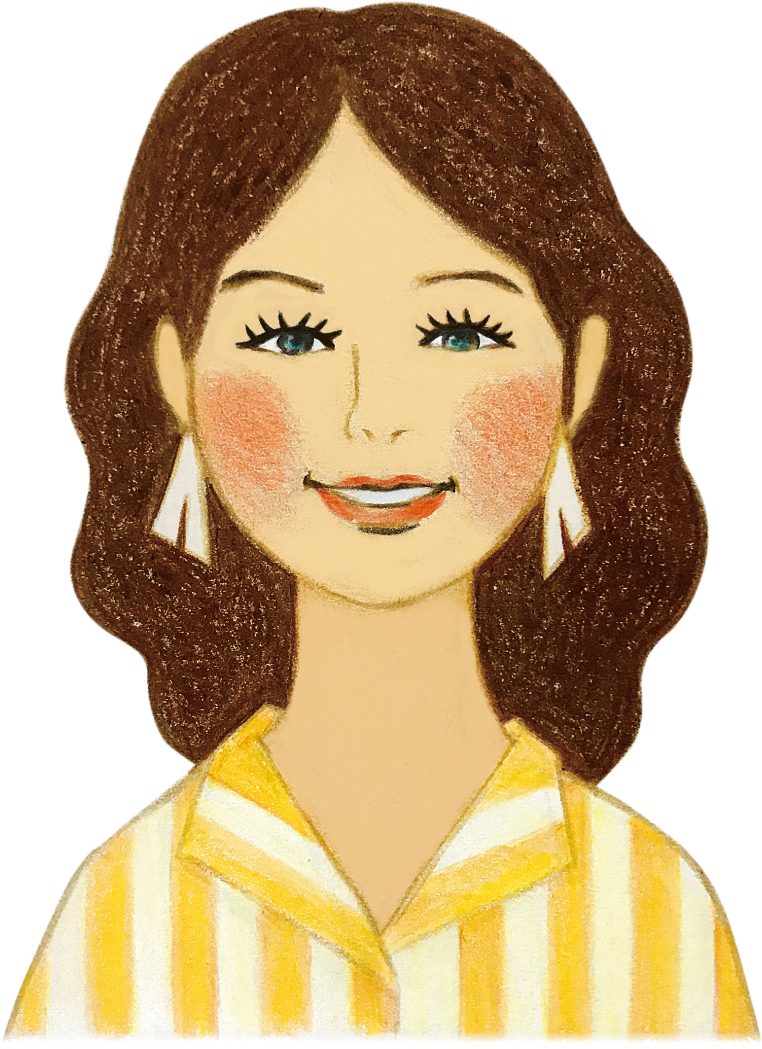Table of Contents
予告編では面白そうと思ったのに本編はそうでもなかった、ということが時折ある。勝手に期待値を上げてしまったこっちの独りよがりでもあるし、何度も劇場で予告編を見ているうちに「いつの間にか本編を見た気になって新鮮に感じられなかった」という錯覚みたいな事態もある。逆に「予告編見る限りでこんな映画だとは思わなかったんだけど?」と言いたくなるくらい良い映画もあって、たかだ予告編されど予告編を思い知ることは多い。現在公開中の「セイント・フランシス」は完全に後者。「もうちょっと上手に予告編作ってくれたらよかったのに…」と思うほど、私の予想や期待を超えていた。
尿漏れパッドが縮めてくれる距離もある
大学を1年で中退しウェイトレスとして働く34歳の女性、ブリジッドはひと夏、フランシスという6歳の女の子のナニーとして仕事を得る。華やかな仕事についていない、結婚していない自分をつい周囲を比較してしまいがちだったブリジッドの人生がフランシスやその両親であるレズビアンカップルとの交流を経て、少しずつ変化する…というのがざっくりとしたあらすじ。あえて無味乾燥な説明をしたのは、このテの作品は今に始まったものではないからだ。
予告編の冒頭、「30代半ばで何をすべきか」とGoogle検索してため息をつく様はまさに
クオーターライフ・クライシス(同年代の人と自分を比べて落ち込んだり、自分らしさを見失って混乱したりする20代後半〜30代が陥りがちな幸福の低迷期)そのもの。
生き惑う姿を表現するにしても随分ベタだな…と感じてしまったのが正直なところだ。
記憶を遡ると「ブリジッド・ジョーンズの日記」に始まり、特に2010年以降は主人公の性別を問わず「無職 家なし 無一文」「がけっぷち人生」みたいなキャッチコピーをつけられる映画が多かったので、「セイント・フランシス」にも既視感があった。
…とここまで全然褒めていないのだが、「登場人物が皆、価値観の合わなさを全く取り繕おうとしない」一点において、私はこの作品を大好きになった。
ブリジッドが作中でナニーとして仕事すること、そして中絶することは本作で主演と脚本を務めたケリー・オサリヴァン自身の体験によるものだ。
お腹の子の父親、ジェイスに「産む気はない」とだけ伝えると「付き合っているわけだし
付き添いたい」と言われ「いや付き合ってないけど」と制するブリジッド。
冷めているのか、虚勢を張って冷めているふりをしているのか常に平静なブリジッドと、力になりたい、僕も動揺しているんだと働きかけるジェイスの温度差に始まり、妊娠・出産、月経や中絶に対する意見の相違が様々な場面で登場する。
片方のママはタンポンを使っていて、もう片方のママは月経カップを使っているの、私も自分に合うものを見つけたいわとブリジッドにぶっちゃけるフランシスは
“Every woman’s body is different”
―女の人の体はすべて違うからね
と結論付ける。6歳(ガキとはあえて言わない)で何言ってんだと思わなくもないが、周囲の大人がオープンに話せる時代になっているのを象徴しているように感じる。
同級生の●●は妊娠したみたいよと実母からやんわり圧をかけられても、ブリジッドは「気候変動だ、核兵器だってこんな不安な時代に子どもなんて産めない」と一点張りし、母親は「あなたが産まれた80年代だって毎日ロシアとの核戦争の危機が報道されていた」と永遠に交わらない会話を続ける。
“It’s reckless”
―無責任よ
“Optimistic”
―楽観的と言ってちょうだい
何気ないけど一番好きなやり取りだ。そして私もかつてはブリジッドのような気持ちを抱いていたのに、完全に母親の側になってしまったなと実感する瞬間でもあった。
また、フランシスの母親2人はカソリック教徒でブリジッドの中絶を肯定的に受け取ることはできずにいる。分かり合えなさは性差や世代、信条など様々なところから生じるものだけど、同時に尿漏れパッド一つで縮まる距離があることもこの作品は教えてくれる。
「共感が大事」とか「相手の立場に立ってみよう」なんて賢しげなことを言わずとも、たった一つの行動で示せる団結がそこにはあったのだ。
返す返すも、ブリジッドとフランシスの絆にばかりフォーカスしている予告編、全然作品の本質じゃないじゃないか、と零したくなるのだった。
ジェンダーギャップ指数上位国でも“あるある”のクオーターライフ・クライシス
少し前に見たノルウェー映画「わたしは最悪」も予告編での印象と本編ががらっと異なる「思てたんと違う」映画だった。これも予告編ではアラサー女性の自分探しという色が強くて、ジェンダーギャップ指数上位常連のノルウェーでこれを撮るんだという意外性があったのだ。
かつて医学部の学生だったユリヤは、医学よりも心理学、いやそれよりも写真に興味がある…とキャリアを転々とし、現在は書店でバイトしている30歳。グラフィックノベル作家として成功している恋人のアクセルから、そろそろ子どもを作らないかと持ちかけられるものの、今はまだ考えられないと抵抗感を示す。このギクシャクした空気がストーリーを大きく動かし、二転三転した結果、思ってもいない結末にあっと驚かされる作品だった。
キッズフレンドリーとか社会福祉とか幸福度などのイメージが先行するけど、北欧諸国にも子どもを欲しがらない女性はいるだろうし、全てのカップルのジェンダー観が一致して常に対等かといえばそうでもないだろう。
もちろん2022年時点でジェンダーギャップ指数146カ国中116位の日本と比べれば断然
進んではいるし、「セイント・フランシス」同様、体に対する自己決定を随所から感じることができる。
…とここまで絶賛しているのだが、劇場鑑賞時はすごくハマった!!大好きな映画!!とならなかったのがこれまた正直な感想なのだ。
ユリヤの逡巡をもう自分ごととして捉えられなくなってしまった、それもある。ユリヤの行動が突飛すぎてついていけない、それもある。だけど一番の要因は、白夜真っただ中のノルウェーの風景があまりに素敵すぎてストーリーそっちのけで見入ってしまったことだ。映像美が集中を阻むなんて、きっと制作側は想像だにしていないだろう。
しかし「セイント・フランシス」を見た今だからこそ振り返って嚙み締められる部分も数々あったし、この2作品には共鳴し、呼応するものがある。そのうち早稲田松竹あたりが2本立て上映してくれるんじゃないかなと一抹の希望を託しているところ(※両作品とも9月頭時点でそれぞれ劇場公開は続いています)
「百聞は一見に如かず」とは言ったもので、予告編だけを見てもその作品の真価は分からないけど、それと同じくらい本編を見てもまだ分からないことっていくらでもあるんだという新鮮な驚きが私にとっては一番の収穫だったかもしれない。
セイント・フランシス
https://www.hark3.com/frances/#modal
わたしは最悪
https://gaga.ne.jp/worstperson/